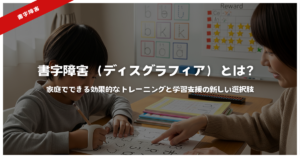書字障害(ディスグラフィア)とは?家庭でできる効果的なトレーニングと学習支援の新しい選択肢
お子さんの「書く」ことに関する悩みは、保護者にとって非常に深刻な問題です。周りの子と同じようにできない姿を見ると、ご自身の育て方を責めてしまったり、将来への不安を感じたりすることもあるかもしれません。
しかし、まず知っていただきたいのは、文字を書くのが極端に苦手なのは、決して本人の努力不足や、保護者の育て方のせいではないということです。その背景には、「書字障害(ディスグラフィア)」と呼ばれる、生まれつきの特性が関係している可能性があります。
この記事では、書字障害の特性を正しく理解し、家庭でできる効果的なトレーニング方法から、専門家によるサポート、そして学習の困難を乗り越えるための新しい選択肢まで、保護者の皆さまの不安に寄り添いながら、具体的かつ専門的な情報をお届けします。
「うちの子も?」書字障害(ディスグラフィア)の主な症状と原因

書字障害は、学習障害(LD)の一種で、知的な発達に遅れがないにもかかわらず、「文字を書く」ことに著しい困難が生じる障害です。まずは、その具体的な症状と原因を正しく理解することから始めましょう。
書字障害のチェックリスト
以下のようなサインが見られる場合、書字障害の可能性が考えられます。複数当てはまる場合は、専門機関への相談を検討してみるのも良いでしょう。
- □ 文字の形や大きさがバラバラで、マスの中に収まらない
- □ 鏡文字や、逆さ文字を頻繁に書く
- □ 漢字の「へん」と「つくり」が逆になるなど、パーツの位置を間違える
- □ 線や点を余分に書いたり、逆に足りなかったりする
- □ 黒板や教科書の文字をノートに書き写すのに非常に時間がかかる(板書が苦手)
- □ 文章を書くときに、助詞(てにをは)を頻繁に間違える、または抜かしてしまう
- □ 作文や日記など、自分の考えを文章にすることが極端に苦手
- □ 筆圧が極端に強い、または弱く、すぐに疲れてしまう
なぜ「書く」のが難しい?書字障害の3つのタイプと原因
書字障害の原因は完全には解明されていませんが、脳機能の特性が関係していると考えられています。文字を書くという行為は、「文字を思い出す」「形を認識する」「体を動かす」といった複数の脳の働きが連携して行われます。書字障害の子どもたちは、この連携のいずれかの部分に困難を抱えているのです。
一般的に、書字障害は以下の3つのタイプに分けられると言われています。
| タイプ | 特徴 | 考えられる原因 |
| 字形(ディスグラフィック)タイプ | 思い描いた文字の形を、正確に書くことが難しい。「なんとなく」の形で覚えてしまい、細かい部分が曖昧になる。 | 視覚情報処理の困難:文字の形を空間的に正確に認識したり、記憶したりすることが苦手。 |
| 綴り(スペリング)タイプ | 音と文字を結びつけるのが苦手。聞いた単語を文字に起こしたり、漢字を正しく思い出したりすることが難しい。 | 音韻処理の困難:言葉を音の単位(音素)に分解したり、文字と音を結びつけたりする働きが弱い。 |
| 運動(モーター)タイプ | 手先が不器用で、思うようにペンを操作できない。筆圧のコントロールや、滑らかな線を書くことが難しい。 | 協調運動の困難:目で見ている情報と、手の動きをスムーズに連動させることが苦手。 |
これらのタイプは、どれか一つだけ当てはまるというより、複数併せ持っているケースも少なくありません。大切なのは、「サボっているのではなく、脳の特性として難しい」と理解し、その特性に合ったアプローチを見つけることです。
家庭でできる!書字障害の特性に合わせたトレーニング法

専門家のサポートは重要ですが、ご家庭でも子どもの特性に合わせて、楽しみながら取り組めるトレーニングがたくさんあります。ここでは、書字障害の改善に有効とされる代表的なアプローチを3つご紹介します。
① 運筆・ボディイメージを高めるトレーニング
文字を書く土台となる「線をコントロールする力」や「体の動きをイメージする力」を養います。
- なぞり書き・点つなぎ: 運筆の基本です。最初は大きな曲線や直線から始め、徐々に迷路や図形など複雑なものに挑戦しましょう。
- 粘土遊び・ひも通し: 手指の巧緻性(器用さ)を高めます。指先を使う感覚を養うことで、筆記具の操作もスムーズになります。
- 体を使った文字書き: 空中に指で文字を書いたり、背中に文字を書いて当てっこゲームをしたりするのも有効です。体の大きな動きと文字の形を結びつけることで、形を記憶しやすくなります。
② ビジョントレーニング
文字を正確に認識するために不可欠な「見る力」を鍛えるトレーニングです。近年の研究では、ビジョントレーニングが読み書き能力の向上に寄与する可能性が示唆されています。
- 眼球運動トレーニング: 指やペン先を目で追いかける練習です。上下左右、斜め、円など、ゆっくり動かす指先を頭を動かさずに目で追うことで、眼球のコントロール能力を高めます。これは、行を飛ばさずに文章を読んだり、板書をスムーズに追いかけたりするために重要です。
- 形や空間を認識するトレーニング:
- 間違い探し・同じ絵探し: 細かい部分に注意を向け、形の違いや同じ形を認識する力を養います。
- パズル・ブロック: 図形を組み合わせたり、空間的な位置関係を把握したりする練習になります。これは、漢字のへんとつくりのバランスを取る力にも繋がります。
③ 音と文字を結びつけるトレーニング
「綴り(スペリング)タイプ」の子どもに特に有効なトレーニングです。
- しりとり・言葉遊び: 言葉の音に親しみ、音の単位を意識するきっかけになります。
- かるた・単語カード: 絵や音と文字を結びつけて覚える練習です。ゲーム感覚で楽しく取り組めます。
- 読み聞かせ: 保護者が文章を読み、子どもが指で文字を追うことで、音と文字が一致していることを視覚的に確認できます。
海外の視点:多感覚アプローチの重要性
海外の教育現場では、書字障害を含む学習障害のある子どもに対し、「多感覚アプローチ(Multisensory Approach)」が広く採用されています。これは、視覚、聴覚、触覚、運動感覚など、複数の感覚を同時に使って学習する方法です。例えば、砂の箱に指で文字を書いたり、ザラザラした文字カードをなぞったりすることで、視覚だけでなく触覚からも文字の形をインプットします。家庭でのトレーニングにおいても、この「多感覚」を意識することで、より高い効果が期待できるでしょう。
これらのトレーニングは、あくまで子どもが「楽しい」と感じる範囲で行うことが最も重要です。無理強いは逆効果になりかねません。焦らず、お子さんのペースに合わせて少しずつ取り組んでみてください。
「書く」以外の選択肢を。デジタル教材がもたらす可能性

家庭でのトレーニングは有効ですが、一方で「書く」練習そのものが、お子さんにとって大きなストレスになっているケースも少なくありません。苦手なことを繰り返し練習させられることで、勉強そのものが嫌いになり、自己肯定感が下がってしまう…。これは、何としても避けたい事態です。
ここで、少し視点を変えてみませんか?
大切なのは、「きれいに書けるようになること」だけでしょうか。それとも、「内容を理解し、学ぶ楽しさを感じること」でしょうか。
もしお子さんが「書く」ことに強い苦痛を感じているなら、無理に書かせることを一旦やめてみるというのも、非常に重要な選択肢です。そして、その代替手段として今、大きな注目を集めているのがICTを活用したデジタル教材です。
なぜデジタル教材が書字障害の子に有効なのか?
デジタル教材は、書字障害の子どもたちが抱える「書く」ことのバリアを取り除き、学習の本質である「理解」に集中させてくれる多くのメリットを持っています。
- 音声読み上げ機能で「聴覚」をサポート
書字障害の子の中には、文字を読むこと(ディスレクシア)にも困難を併せ持つ子が多くいます。問題文や解説を音声で読み上げてくれる機能は、そんな子にとってまさに救世主です。目で追うだけでなく、耳から情報を入れることで、内容理解が格段に進みます。 - 選択式問題で「書く」負担をゼロに
答えがわかっているのに、文字を書くのが億劫で先に進めない…。そんなもどかしさを、デジタル教材は解消してくれます。クリックやタップで答えられる選択式の問題なら、「書く」という作業を介さず、知識の確認や定着をスムーズに行えます。 - 視覚的にわかりやすいアニメーション講義
文章を読むのが苦手な子にとって、動きや色、音を伴うアニメーションでの解説は、内容を直感的に理解する大きな助けとなります。視覚的な情報処理が得意な子には特に効果的です。
「わかる!」喜びが自信に変わる。デジタル教材「天神」という選択
数あるデジタル教材の中でも、特に書字障害や発達障害のあるお子さんの特性に配慮した設計で評価されているのが、私たち「天神」です。
「天神」は、まさに「書く」ことの困難を乗り越え、「学ぶ楽しさ」を取り戻すために開発されたデジタル教材です。
- 専門家も推薦する、発達障害に配慮した機能
「天神」は、障害児教育の専門家である山内康彦氏(障がい児成長支援協会 代表理事)からも推薦を受けています。その理由は、書字障害の子どもたちが安心して学べる数々の機能にあります。- 音声読み上げと自動ハイライト(小学生版): 問題文や選択肢、ヒント、解説まで、音声で読み上げてくれます。さらに、読んでいる箇所がハイライト表示されるため、どこを読んでいるか視覚的にもわかりやすく、聴覚と視覚の両面から理解を強力にサポートします。保護者の方からは、「この機能があるかないかで、子どもの集中力が全く違う」という声を多数いただいています。
- 超スモールステップで成功体験を積める: 「天神」は、学力の凹凸を前提に設計されています。一人ひとりの理解度に合わせて、非常に細かいステップで学習を進められるため、「できた!」「わかった!」という成功体験を積み重ねやすくなっています。強制的に同じ問題を繰り返させることはなく、お子さん自身が「もう一度やる」か「次に進む」かを選べる点も、自己肯定感を育む上で重要なポイントです。
- 直感的な操作と選択式の出題: 書き込み式の教材では操作が難しかったお子さんも、「天神」のシンプルなクリック・タップ操作ならスムーズに取り組めます。ストレスなく学習に集中できる環境を提供します。
もし、お子さんが「書く」ことの壁にぶつかり、学習への意欲を失いかけているなら、一度「書く」ことから離れて、「天神」のようなデジタル教材で「わかる喜び」を体験させてあげることを検討してみてはいかがでしょうか。
学校や専門機関との連携で、子どもの学習環境を整える
家庭での取り組みと並行して、学校や専門機関と連携し、お子さんにとって最適な学習環境を整えていくことも非常に重要です。
学校に求められる「合理的配慮」とは?
2016年に施行(2024年に改正施行)された「障害者差別解消法」により、学校は障害のある子どもに対して「合理的配慮」を提供することが義務付けられました。書字障害のある子どもの場合、以下のような配慮が考えられます。
- 板書の写真撮影許可: ノートに書き写す代わりに、タブレットやカメラで撮影することを許可してもらう。
- デジタル教科書の活用: 紙の教科書ではなく、読み上げ機能や文字拡大機能のあるデジタル教科書の使用を認めてもらう。
- テストの解答方法の変更: 筆記ではなく、口頭での解答や、パソコンでの入力を許可してもらう。
- 時間の延長: テストや課題の提出時間を通常より長く設定してもらう。
これらの配慮を求める際は、まず担任の先生やスクールカウンセラー、特別支援教育コーディネーターに相談してみましょう。
「天神」は不登校児の出席扱いにも対応
書字の困難さがきっかけで学校に行きづらくなり、不登校になってしまうケースも少なくありません。「天神」は、文部科学省のガイドラインに沿っており、ICT等を活用した家庭学習を出席扱いとするための要件を満たしています。学習の進捗状況をまとめた「学習報告書」をワンタッチで出力できるため、学校への提出もスムーズです。学習の遅れを取り戻しながら、出席日数も確保できる、心強い味方となります。
どこに相談すればいい?専門機関の役割
家庭や学校だけで悩みを抱え込む必要はありません。以下のような専門機関が、保護者の強い味方になってくれます。
- 市町村の教育支援センター(適応指導教室): 学習支援や教育相談を行っています。
- 発達障害者支援センター: 発達障害に関する総合的な相談窓口です。
- 医療機関(小児科、児童精神科、リハビリテーション科など): 診断や、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)による専門的な訓練を受けることができます。
診断を受けることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、診断名は「レッテル」ではなく、お子さんの特性を正しく理解し、適切な支援を受けるための「コンパス」です。一人で抱え込まず、ぜひ専門家の力を借りてください。
保護者の不安に寄り添う。「天神」の無料サポート体制

ここまで様々な情報をお伝えしてきましたが、それでも「うちの子に合うかどうかわからない」「何から始めたらいいの?」といった不安は尽きないことと思います。
「天神」は、教材を売って終わり、ではありません。お子さんと保護者一人ひとりの悩みに寄り添い、ゴールまで伴走するサポート体制を何よりも大切にしています。
- 児童発達支援士などの有資格者が対応: ご契約前はもちろん、ご契約後も、学習の進め方や利用方法に関する相談はすべて無料です。お電話口では、児童発達支援士や発達障害支援アドバイザーなどの資格を持つ専門スタッフが、あなたの悩みに直接お答えします(自動音声ではありません)。
- しつこい営業は一切なし、安心の無料体験: 「天神」の良さを実感いただくために、まずは無料体験をおすすめしています。体験のためにPCやタブレットがなくても、体験専用のパソコンを無料でお貸し出し(往復送料も不要)。クレジットカードの登録も必要ありません。全学年・全教科をじっくり試せるので、「うちの子にはどこまで必要か」をしっかり見極められます。体験後、「購入予定なし」とご回答いただいた方には、原則ご連絡いたしませんので、安心してお試しください。
- 兄弟は何人でも無料。家計にも優しい買い切り型: 「天神」は、一度ご購入いただければ、ご兄弟・ご姉妹は何人でも無料でご利用いただけます。それぞれの進捗状況は個別に管理されるので安心です。月額費用の負担がない買い切り型なので、長期的に見ても家庭の教育コストを抑えることができます。
書くことの苦しみを、「わかる」喜びに変えよう
お子さんの書字障害の悩みに、一人で立ち向かう必要はありません。
大切なのは、お子さんの特性を正しく理解し、「書く」ことへのプレッシャーから解放してあげることです。そして、「わかる」「できる」という学びの本来の楽しさを、もう一度取り戻させてあげることです。
家庭でできるトレーニングを試しながら、学校や専門家と連携し、そして「天神」のようなデジタル教材の力を借りる。こうした多角的なアプローチが、お子さんの未来を明るく照らす鍵となります。
「書く」ことの苦しみが、「わかる」喜びに変わる。
その第一歩を、まずは「天神」の無料体験から始めてみませんか? お子さんの今まで見えなかった可能性が、そこには広がっているかもしれません。
【よくある質問】
Q:PCやタブレットがなくても体験できますか?
A:はい。体験専用のパソコンを無料でお貸し出ししています(往復送料も不要です)。
Q:体験後にしつこく営業されますか?
A:いいえ。「購入予定なし」とアンケートで回答された方には、原則としてご連絡しておりません。安心してお試しいただけます。
Q:デジタルが苦手な子にも使えますか?
A:はい。操作はクリックやタップが中心で、直感的でシンプルです。音声やアニメーション、選択式の出題で、お子さんのストレスが少ないように設計されています。