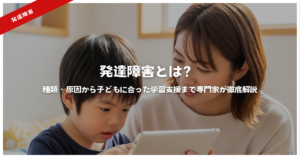発達障害とは?種類・原因から子どもに合った学習支援まで専門家が徹底解説
子どもの成長を見守る中で、このような疑問や不安を抱える保護者の方は少なくありません。インターネットやテレビで「発達障害」という言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味や、子どもにどう接すればよいのか分からず、一人で悩みを抱え込んでしまうこともあります。
この記事では、小学生・中学生のお子さんを持つ保護者の方向けに、発達障害の基本的な知識から、お子さんの特性に合わせた具体的な学習支援の方法まで、専門的な視点から分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、発達障害への理解が深まるだけでなく、お子さんの持つ可能性を最大限に引き出すための具体的なヒントが見つかるはずです。不安を安心に変え、お子さんと一緒に前向きな一歩を踏み出すための羅針盤として、ぜひご活用ください。
- 発達障害の正確な定義と「育て方のせいではない」という事実
- 代表的な3つの種類(ASD・ADHD・LD)の特性と見分け方
- なぜ学習でつまずきやすいのか?特性別にみる脳のメカニズム
- 家庭でできる効果的な学習サポートの方法
- お子さんの特性を強みに変えるデジタル教材の活用法
発達障害とは?まず知っておきたい基本知識

発達障害は、病気ではなく「生まれつきの脳機能の発達のかたより」によるものです。親の育て方やしつけ、愛情不足が原因ではありません。まずはこの点をしっかりと理解し、保護者の方がご自身を責めないことが何よりも大切です。
発達障害のある人は、得意なことと苦手なことの差(発達の凹凸)が非常に大きいという特徴があります。例えば、記憶力は抜群なのに、人とのコミュニケーションは極端に苦手、といった具合です。この特性が、学校生活や社会生活の中で様々な困難を生じさせる原因となります。
発達障害の「原因」は?
現在、発達障害の明確な原因は完全には解明されていませんが、多くの研究で遺伝的な要因が複雑に関与する、生まれつきの脳機能の障害であると考えられています。決して、妊娠中の過ごし方や、生まれてからの育て方が直接の原因となるわけではありません。
アメリカ疾病予防管理センター(CDC)も、「発達障害は、個人の育て方や経済的な状況によって引き起こされるものではない」と明言しており、遺伝的要因と、その他(妊娠中の特定の感染症など)の環境要因が複雑に絡み合って発現すると考えられています。
大切なのは、「原因探し」に時間を費やすのではなく、「その子の特性を正しく理解し、どうすればその子が生きやすくなるか」という視点でサポートを考えることです。
「グレーゾーン」とは?
診断基準を完全には満たさないものの、発達障害の特性が見られる状態を「グレーゾーン」と呼ぶことがあります。例えば、「ADHDと診断されるほどではないけれど、不注意や多動の傾向が強い」といったケースです。
グレーゾーンの子どもたちも、診断名のある子どもたちと同様に、学習面や生活面で困難を抱えていることが少なくありません。しかし、診断がないために公的な支援を受けにくく、周囲からも「本人の努力不足」「わがまま」と誤解されやすいという課題があります。
診断名のあるなしにかかわらず、お子さんが何かに困っているのであれば、その特性に合わせたサポートをしてあげることが重要です。
【種類別】発達障害の主な3つのタイプとその特性
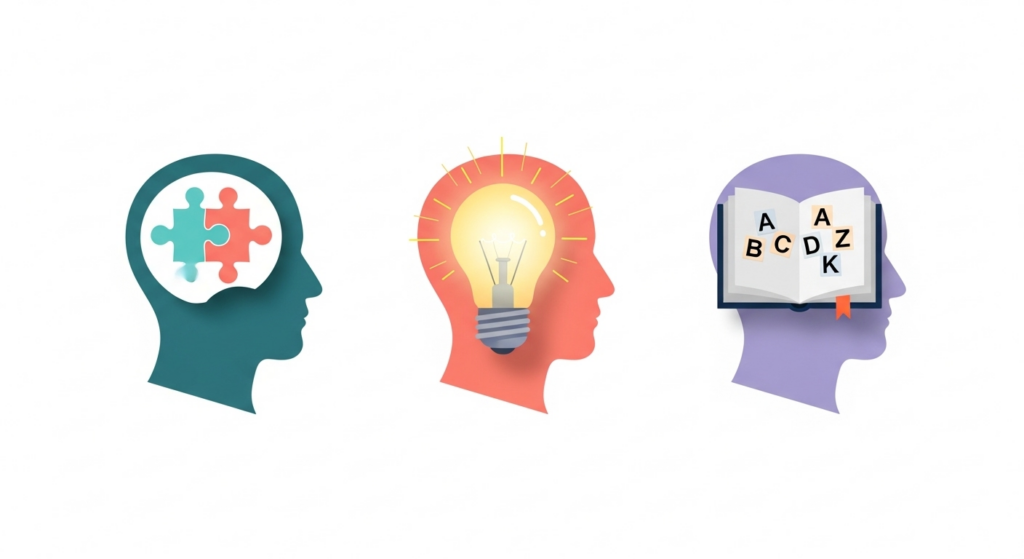
発達障害は、主に以下の3つのタイプに分類されます。ただし、これらの特性が複数重なって現れることも珍しくありません。お子さんの行動を理解するための「ものさし」として、それぞれの特徴を見ていきましょう。
① ASD(自閉スペクトラム症)
ASDは、主に「対人関係やコミュニケーションの困難」と「限定された興味やこだわり」という2つの大きな特性を持ちます。
主な特性
- 相手の気持ちを察したり、空気を読んだりするのが苦手
- 比喩や皮肉が通じにくい
- 一方的に自分の話したいことだけを話してしまう
- 視線を合わせるのが苦手
- 特定の手順やルールに強くこだわる(例:いつも同じ道を通らないと不安になる)
- 急な予定変更に対応するのが難しい
- 興味の範囲が非常に狭く、好きなことには驚異的な集中力と知識を発揮する
- 特定の音や光、匂い、触覚などを極端に嫌がる(感覚過敏)
- 逆に、痛みや暑さ・寒さなどを感じにくい(感覚鈍麻)
- 先生の指示が曖昧だと、何をすれば良いか分からなくなる(例:「各自、いい感じに進めておいて」)
- 文章問題で、登場人物の気持ちを推測する問題が苦手
- 興味のない科目には全く集中できない
② ADHD(注意欠如・多動症)
ADHDは、「不注意(集中力がない)」「多動性(じっとしていられない)」「衝動性(思いついたら行動してしまう)」の3つの特性が特徴です。
主な特性
- 不注意:
- 授業中など、集中力を持続させることが難しい
- 忘れ物や失くし物が多い
- ケアレスミスが多い
- 話を聞いていないように見えることがある
- 多動性:
- 授業中に席を立って歩き回る
- 常にそわそわ、もじもじしている
- おしゃべりが止まらない
- 衝動性:
- 質問が終わる前に答えてしまう
- 順番を待つことが苦手
- 相手の話を遮って話し始める
- 長時間の授業や宿題に集中できない
- 問題文を最後まで読まずに答えてしまい、ミスをする
- 簡単な計算ミスや漢字の書き間違いが多い
③ SLD(限局性学習症)/LD(学習障害)
SLD/LDは、知的発達に遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」といった能力の習得と使用に著しい困難を示す状態です。
主な特性
- 読字障害(ディスレクシア):
- 文字を一つひとつ拾って読むため、読むのが非常に遅い
- 文章をどこで区切って良いか分からず、内容が頭に入らない
- 似た形の文字(「わ」と「ね」など)を読み間違える
- 書字障害(ディスグラフィア):
- 鏡文字を書いたり、漢字のへんとつくりを逆に書いたりする
- マスの中に文字をバランス良く書くのが苦手
- 文字の形を思い出すのに時間がかかる
- 算数障害(ディスカリキュリア):
- 数の大小や順序の理解が難しい
- 繰り上がり、繰り下がりの計算が苦手
- 文章問題の意味を理解するのが難しい
- 教科書を音読させられるのが苦痛
- 板書を書き写すのに時間がかかり、授業についていけない
- 筆算で桁をそろえられない
これらの特性は、本人の「怠け」や「努力不足」ではありません。脳の特性によるものだと理解することが、適切なサポートへの第一歩となります。
なぜ勉強が苦手?発達障害と学習の困難を結びつけるメカニズム
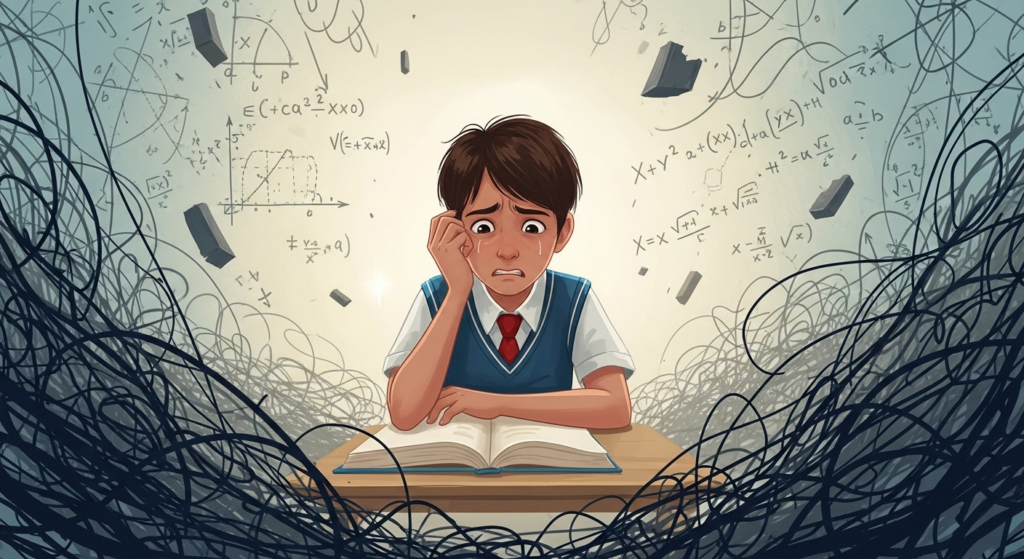
発達障害のある子どもが学習につまずくのは、決して知能が低いからではありません。その子特有の「認知の特性」と、一般的な学校教育の「画一的な進め方」との間にミスマッチが生じることが大きな原因です。
脳科学研究から見る学習の困難
近年の脳科学研究では、発達障害のある人の脳の働き方が、定型発達の人とは異なることが分かってきています。
例えば、ADHDの研究では、行動のコントロールや注意の持続に関わる前頭前野の働きが弱い傾向にあることが示唆されています。これにより、外部からの刺激に気を取られやすくなったり、行動の抑制が効きにくくなったりすると考えられます。
また、読字障害(ディスレクシア)の研究では、文字の形と音を結びつける役割を担う脳の領域(左半球の側頭-頭頂領域など)の活動が低いことが報告されています。これは、文字を読む際に脳が非効率的なルートを使っているような状態で、読むことに多大なエネルギーを消耗してしまうのです。
特性別にみる「つまずき」の背景
| 特性 | 内容 | |
| ASD | 見通しの立たない不安 | 授業の全体像やゴールが見えないと、「何をどこまでやればいいのか」が分からず不安になり、パニックに陥ることがあります。 |
| 暗黙のルールの不理解 | 「行間を読む」「空気を読む」といった国語の問題や、集団でのディスカッションが苦手です。ルールが明確でないと、どう振る舞って良いか分かりません。 | |
| ADHD | ワーキングメモリの弱さ | ワーキングメモリとは、情報を一時的に記憶し、同時に処理する能力のことです。ADHDの特性があると、この機能が弱い傾向にあります。例えば、長い文章問題を読むと、最後の部分を読む頃には最初の内容を忘れてしまい、話の筋が追えなくなります。 |
| 実行機能の困難 | 計画を立てて、順序良く物事を進める「実行機能」に課題を抱えることがあります。宿題をどこから手をつけていいか分からず、結局手つかずのまま…というケースも少なくありません。 | |
| SLD/LD | 自動化の困難 | 定型発達の子どもは、反復練習によって読み書きや計算を無意識に(自動的に)行えるようになります。しかし、SLD/LDの子どもは、この「自動化」がうまくいきません。一文字読む、一画書くたびに、脳に大きな負担がかかっている状態です。 |
こうした学習上の困難が続くと、「自分は何をやってもダメだ」という自己否定感につながり、不登校やうつ病といった二次障害を引き起こすリスクも高まります。そうなる前に、お子さんの特性に合った学習環境を整えてあげることが不可欠です。
家庭でできる!発達障害のある子どもの学習を支える5つのアプローチ

発達障害のある子どもの学習支援で最も大切なのは、「できないこと」を責めるのではなく、「できること」を増やすための環境を整えることです。ここでは、家庭ですぐに実践できる5つのアプローチをご紹介します。
特にADHDの特性がある子どもは、視覚や聴覚からの刺激に注意を奪われやすい傾向があります。
- 物理的な環境: 勉強する机の上には、学習に必要なもの以外は置かない。テレビを消し、おもちゃなどが視界に入らないようにする。
- 時間的な環境: 「15分勉強したら5分休憩」のように時間を区切り、集中と休憩のメリハリをつける。
ASDの特性がある子どもは、ゴールが見えないと不安になります。また、ADHDの特性がある子どもは、大きな課題を前にするとどこから手をつけていいか分からなくなります。
- 課題の細分化: 「漢字ドリルをやる」ではなく、「①まず漢字を3つ覚える」「②なぞり書きを3回する」「③例文を1つ読む」のように、タスクを細かく分解してリスト化する。
- スケジュールの視覚化: 言葉だけでなく、絵や図、ホワイトボードなどを使って「やることリスト」を見える化する。終わったタスクにチェックを入れることで、達成感も得られます。
抽象的な指示は、発達障害のある子どもにとって理解が難しい場合があります。
- NG例: 「ちゃんと勉強しなさい」「しっかり復習しておいて」
- OK例: 「算数の教科書15ページの問題①を、ノートに解いて」
一度に多くの指示を出すと混乱してしまうため、「1つの指示が終わったら次」を徹底しましょう。
- 聴覚優位の子: 口頭で説明したり、教材を音読してあげたりすると理解が進みます。
- 視覚優位の子: 図やイラスト、動画など、視覚的な情報を使って説明すると効果的です。
特に、読み書きに困難(SLD/LD)がある場合、教科書を読む代わりに音声で聞くという方法は非常に有効です。
結果(100点を取れたか)だけでなく、過程(机に向かって5分集中できた、1問でも解こうと努力した)を具体的に褒めることが自己肯定感を育みます。
他人と比較するのではなく、「昨日の自分より、これができるようになったね」という本人の成長を認め、伝えてあげることが大切です。
これらのアプローチをシステム化した教材「天神」
そう感じる保護者の方も多いのではないでしょうか。
実は、これらの学習支援のポイントをシステムとして網羅し、誰でも簡単に実践できるように設計されたデジタル教材があります。それが、家庭学習用デジタル教材「天神」です。
- 超スモールステップで安心: 「天神」は、学習内容を非常に細かく分解。1つ数分で終わる超スモールステップで構成されているため、ADHDの子どもでも集中力が続きやすく、ASDの子どもも見通しを持って安心して取り組めます。
- 視覚・聴覚で理解をサポート: アニメーションによる講義や、豊富なイラスト・画像で視覚的に理解を助けます。さらに、問題文からヒント、解説まで音声で読み上げる機能(※小学生版)は、読み書きに困難のあるSLD/LDの子どもや、聴覚優位の子どもにとって絶大な効果を発揮します。「音声読み上げがあるかないかで、集中力が全く違う」という保護者の声も多数寄せられています。
- 本人のペースを尊重する「自己決定権」: 他の教材にありがちな強制的な反復学習はなく、子ども自身が「もう一度やるか」「次に進むか」を選べます。この「自己決定権」が、学習への主体性を育みます。
「天神」は、障害児教育の専門家である障がい児成長支援協会 代表理事・山内康彦氏からも推薦されており、発達障害や学習障害のある子どもたちが安心して取り組める構成が高く評価されています。
一般的な塾や教材が合わなかったお子さんでも、「天神なら続けられる」というケースは少なくありません。
5. 一人で悩まないで。頼れる相談先と支援制度

お子さんの発達について悩みや不安を感じたら、一人で抱え込まずに専門機関に相談することが大切です。
主な相談先
- 市区町村の保健センター・子育て支援センター: 最も身近な相談窓口。保健師や専門の相談員が話を聞き、必要に応じて専門機関につないでくれます。
- 児童相談所: 18歳未満の子どもに関するあらゆる相談に対応しています。
- 発達障害者支援センター: 発達障害に特化した専門的な相談支援機関。都道府県・指定都市に設置されています。
- 医療機関(小児科、児童精神科など): 診断を希望する場合や、医学的な見地からのアドバイスが欲しい場合に受診します。
学校との連携と「出席扱い」制度
学校生活での困難については、担任の先生やスクールカウンセラー、特別支援教育コーディネーターに相談し、連携してサポート体制を築くことが重要です。
また、不登校の状態にあるお子さんでも、自宅でICT等を活用した学習を行い、一定の要件を満たすことで、学校長が指導要録上の「出席扱い」と判断できる制度があります。
デジタル教材「天神」は、この出席扱い制度の要件を満たすために必要な「学習報告書」をワンタッチで簡単に出力できる機能を備えています。これにより、家庭での学習が公的に認められ、お子さんの自信回復や学校復帰へのスムーズな橋渡しにつながる可能性があります。
お子さんの「特性」は「強み」になる
発達障害は、決してネガティブなだけの側面を持つものではありません。
ASDの「こだわり」は、特定の分野での「専門性」や「探求心」につながります。ADHDの「多動性」や「衝動性」は、「行動力」や「独創的なアイデア」の源泉となり得ます。SLD/LDの困難を乗り越える過程で培われる「工夫する力」や「困難に立ち向かう精神力」は、何物にも代えがたい財産です。
重要なのは、画一的な物差しで子どもの能力を測るのではなく、その子の特性を正しく理解し、凹んだ部分をサポートしながら、秀でた部分を存分に伸ばしてあげることです。デジタル教材「天神」は、まさにその思想を形にした教材です。
- 学力に合わせた無学年制: 小学生なら1~6年生、中学生なら1~3年生の全範囲を自由に学習可能。苦手な単元はさかのぼって基礎固めを、得意な教科はどんどん先取り学習ができます。
- 買い切り型で経済的&兄弟無料: 一度購入すれば、月額費用はかかりません。さらに、ご兄弟・ご姉妹は何人でも無料で利用可能。一人ひとりの進捗を個別に管理できるため、ご家庭全体の教育コストを抑えながら、すべてのお子さんに最適な学びを提供できます。
- 安心の無料体験と専門サポート: 「うちの子に合うか分からない」という不安に応えるため、「天神」では全学年・全教科を試せる無料体験を実施しています。パソコンがないご家庭には体験用のPCを無料でお貸し出し(往復送料も不要)。クレジットカード登録も不要で、体験後にしつこい営業もありません。
契約後も、児童発達支援士などの有資格者が在籍する専門スタッフが、電話やメールで無料で学習相談に乗ってくれるなど、サポート体制も万全です。
お子さんの学習に関する悩み、発達に関する不安。「天神」は、そんな保護者の方々に寄り添い、お子さんの持つ無限の可能性を引き出すための強力なパートナーとなります。
まずは無料体験で、「天神」がお子さんの学習をどう変えるのか、その目で確かめてみませんか?お子さんが「これならできる!」と笑顔になる瞬間が、きっとそこにあります。
▼▼▼ クレカ登録不要!PC無料貸出あり!まずは無料体験から ▼▼▼
【よくある質問】