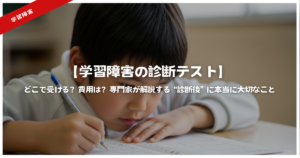【学習障害の診断テスト】どこで受ける?費用は?専門家が解説する“診断後”に本当に大切なこと
お子さんの学習について、このような悩みを抱えていませんか? もしかしたら、それは本人の努力不足や怠慢ではなく、「学習障害(LD: Learning Disabilities)」の特性によるものかもしれません。
学習障害とは、知的な発達に遅れはないものの、「読む」「書く」「計算する」といった特定の能力を学んだり使ったりすることに著しい困難を示す発達障害の一つです。
この記事では、お子さんの学習困難に悩む保護者の方へ向けて、学習障害の可能性を知るためのセルフチェックリストから、専門機関で行われる診断テストの具体的な内容、そして診断後の家庭での支援方法までを、専門的な知見を交えながら分かりやすく解説します。
診断は怖いもの、というイメージがあるかもしれません。しかし、それは「できないこと」のレッテルを貼るためではなく、お子さんの特性を正しく理解し、その子に合った最適なサポートを見つけるための「始まり」なのです。この記事が、その大切な一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
もしかして学習障害?家庭でできるセルフチェックリスト

まず、ご家庭でできるチェックリストをご紹介します。ただし、これはあくまで学習障害の「可能性」に気づくための目安であり、これだけで診断が確定するものではありません。いくつかの項目に当てはまるからといって、過度に心配せず、お子さんを客観的に理解するための一つの材料としてご活用ください。
【小学生向け】チェックリスト
□ 文字を一つひとつ拾うように、たどたどしく読む
□ 単語や文末などを飛ばしたり、勝手な想像で読んだりする
□ どこを読んでいるのか分からなくなり、同じ場所を何度も読んでしまう
□ 文章の内容を正確に理解するのが難しい
□ 「ぬ」と「め」、「わ」と「ね」など、形の似た文字をよく間違える
□ 鏡文字(左右反転した文字)を書くことが多い
□ 文法的な誤り(てにをはなど)が多い
□ 黒板や教科書の文字をノートに書き写すのに、非常に時間がかかる
□ 簡単な計算でも指を使わないとできない
□ 繰り上がり、繰り下がりの計算が苦手
□ 筆算の際、位をそろえて書くことができない
□ 文章問題の意味を理解するのが難しく、式を立てられない
【中学生向け】チェックリスト
中学生になると、学習内容が高度化・複雑化するため、困難さがより顕著になることがあります。
□ 教科書の音読がスムーズにできず、内容の理解に時間がかかる
□ 英語の単語を覚えることや、英文の読解が極端に苦手
□ 数学の図形問題や、証明問題の概念が理解しにくい
□ レポートや作文など、自分の考えを文章にまとめることが困難
□ 板書を写すのが遅く、授業についていくのが難しい
これらの項目に多く当てはまり、ご心配な場合は、一人で抱え込まずに専門機関へ相談することを検討してみましょう。
学習障害の診断はどこで?相談できる専門機関
学習障害の診断や相談は、以下のような専門機関で行うことができます。
- 市町村の保健センター、子育て支援センター: 乳幼児健診のフォローアップや、発達に関する初期相談窓口。
- 児童発達支援センター、発達障害者支援センター: 専門的な相談、発達検査、支援プログラムの提供などを行う中核機関。
- 教育支援センター(適応指導教室): 学校と連携し、学習面や心理面のサポートを提供。
- 医療機関 : 小児科、児童精神科、小児神経科など、子どもの発達を専門とする診療科。
- 学校 :担任の先生や、スクールカウンセラー、特別支援教育コーディネーターに相談するのも有効です。学校での様子を一番よく知っているため、具体的なアドバイスや適切な機関への橋渡しをしてくれることがあります。
どこに相談すれば良いか迷った際は、まずはお住まいの地域の発達障害者支援センターや保健センターに電話してみるのが良いでしょう。そこから、お子さんの状況に合った機関を紹介してもらえます。
診断の目的は、お子さんを型にはめることではありません。客観的なデータを通じて「得意なこと」と「苦手なこと」の凹凸を正確に把握し、その子に合った学習方法や環境を整えるための羅針盤を手に入れることです。
専門機関で行われる「診断テスト」の具体的な内容と流れ

学習障害の診断は、単一のテスト結果だけで判断されるわけではありません。保護者からの聞き取り(生育歴、家庭や学校での様子)、本人の行動観察、そして複数の心理検査の結果を総合的に評価して、慎重に行われます。
代表的な心理検査(診断テスト)
知能検査(例:WISC-V 知能検査)
何がわかるか?: これは「知能指数(IQ)」という一つの数値を見るだけのものではありません。言語理解、視空間認知、ワーキングメモリ、処理速度といった、学習の土台となる様々な認知能力を測定します。学習障害の場合、全体のIQは平均的でも、これらの能力間に大きな差(凹凸)が見られることが多く、「なぜ学習につまずくのか」の原因を探る上で非常に重要な検査です。
読み書きに関する検査(例:STRAW-R 読み書きスクリーニング検査)
何がわかるか?: カナや漢字の読み書きの正確さや速さを、学年相応のレベルと比較して評価します。音読の流暢さ、文字の形の正確さなどを客観的に測定し、読字障害(ディスレクシア)や書字表出障害(ディスグラフィア)の特性を把握します。
診断までの流れと費用
機関に連絡し、初診の予約を取ります。
保護者から、お子さんのこれまでの様子や困りごとについて詳しく聞き取ります。
臨床心理士などの専門家が、お子さんと1対1で複数の検査を数回に分けて行います。
検査結果を分析し、医師や心理士から詳しい説明(フィードバック)を受けます。得意なこと、苦手なこと、そして今後の支援方針について話し合います。
すべての情報を統合し、診断がなされます。学校への提出が必要な場合、報告書(意見書)を作成してもらうことも可能です。
<費用について>
- 医療機関の場合: 診察は保険適用ですが、心理検査やカウンセリングは自費診療となる場合があります。全額自費の場合、数万円程度かかることもあります。事前に医療機関に確認しましょう。
- 公的機関の場合: 児童発達支援センターなどでは、相談や検査が原則無料、または低額で受けられることが多いです。ただし、予約が数ヶ月待ちになることもあります。
診断の先にあるもの:学習障害への理解を深める
診断を受けることで、お子さんが抱える困難の正体が明らかになります。学習障害は、主に以下の3つのタイプに分類されます。
- 読字障害(ディスレクシア): 文字を読むことに困難がある。
- 書字表出障害(ディスグラフィア): 文字を書くことに困難がある。
- 算数障害(ディスカリキュリア): 計算や数量の理解に困難がある。
これらの困難は、脳機能の特性によるものであり、本人のやる気や育て方の問題ではありません。この事実を理解することが、適切な支援の第一歩となります。
海外の研究が示す「多感覚学習」の重要性
学習障害への支援において、世界的に注目されているのが「マルチセンサリー(多感覚)アプローチ」です。米国の学習障害に関する中核機関であるNational Center for Learning Disabilities (NCLD) は、学習障害のある子どもたちへの指導法として、視覚、聴覚、触覚・運動感覚など、複数の感覚を同時に活用することの有効性を強調しています。
例えば、
- 単に文字を見る(視覚)だけでなく、
- その文字の音を聞き(聴覚)、
- 指でなぞったり空中に書いたりする(触覚・運動感覚)
というように、複数の感覚経路から情報を取り入れることで、脳の様々な領域が活性化し、記憶への定着が促されるのです。これは、一つの経路(例:視覚)に困難を抱えていても、他の得意な感覚がそれを補うことができるため、学習障害のある子にとって特に効果的な方法とされています。
「早期発見・早期支援」が、お子さんの自尊心を守り、「自分はダメなんだ」という二次的な心理的問題(不登校、意欲低下など)を防ぐ上で極めて重要であることも、多くの研究で指摘されています。
家庭でできる学習支援|子どもに合った学びの見つけ方

診断結果は「弱点リスト」ではなく、「お子さん専用の取扱説明書」です。これを活かし、ご家庭でお子さんが安心して学べる環境を整えていきましょう。
家庭学習で意識したい3つのポイント
- スモールステップで成功体験を積ませる: 難しい課題を一度にやらせるのではなく、ごく簡単なステップに分解します。「これならできる!」という小さな成功体験の積み重ねが、学習意欲の源泉になります。
- 本人の得意な感覚を活かす: 前述の「多感覚アプローチ」を家庭で実践します。耳からの情報処理が得意な子には音声教材を、図や映像で理解するのが得意な子には動画やイラストを活用するなど、インプットの方法を工夫します。
- 自己肯定感を育む: 結果だけを評価するのではなく、「粘り強く取り組んだね」「違う方法を試してみたんだね」と、プロセスを具体的に褒めましょう。また、「これをやりなさい」という強制ではなく、「どっちからやってみる?」と本人に選択させる場面を作ることも、主体性を育む上で大切です。
しかし、これらのポイントを保護者の方が毎日の学習で実践し続けるのは、並大抵のことではありません。そこで、こうした理想的な学習環境をシステムとして提供してくれるデジタル教材を活用するのも、非常に賢明な選択肢です。
これらのポイントをすべて満たす「天神」という選択肢
数ある教材の中でも、学習障害やその傾向があるお子さんの家庭学習ツールとして、デジタル教材「天神」が多くのご家庭で選ばれています。その理由は、「天神」の設計思想が、まさに学習障害のある子に必要なサポートと合致しているからです。
信頼できる専門家のお墨付き
「天神」は、障害児教育の専門家である障がい児成長支援協会 代表理事・山内康彦氏からも推薦を受けている教材です。専門的な知見に基づいた設計が、安心感と信頼に繋がっています。
学力の凹凸に完全対応する「無学年式スモールステップ」
「天神」は、お子さんの得意な教科は先取り学習で伸ばし、苦手な単元は前の学年にさかのぼって、本当に理解できる場所からスタートできます。一つひとつのステップが非常に細かく設計されているため、無理なく「できた!」を積み重ねられます。
読み書きが苦手でも安心の「多感覚アプローチ」
アニメーションによる講義(視覚)に加え、問題文・ヒント・解説の丁寧な音声読み上げ機能(聴覚)が搭載されています(※)。さらに、読み上げ箇所が自動でハイライト表示されるため、どこを読んでいるか視覚的にもわかりやすく、ディスレクシアの特性がある子も直感的に内容を理解できます。この音声読み上げ機能は、特に小学生版で「集中力が全然違う」と保護者から絶大な支持を得ています。
(※2025年7月現在、音声読み上げ機能は小学生版で標準対応、中学生版は非対応です)
子どもの自己肯定感を守る設計
他社の教材にありがちな、間違えたら同じ問題を強制的に繰り返させる、といった仕組みがありません。「天神」では、やり直すかどうかを子ども自身が選べます。シンプルな操作性と合わせて、学習へのストレスを最小限に抑え、自分で学習を進める主体性を育みます。
不登校支援や家計にも優しい制度
不登校のお子さんの出席扱い認定に必要な「学習報告書」をワンタッチで出力でき、学校への提出もスムーズです。また、一度購入すれば月額料金がかからない「買い切り型」で、ご兄弟・ご姉妹は何人でも無料で利用可能。長期的に見ても、家庭の教育コストを大きく抑えることができます。
まずは無料で試してみよう|「天神」の無料体験ガイド
「うちの子に本当に合うのだろうか?」
そう思われたなら、まずは無料体験でお子さんの反応を確かめてみるのが一番です。
- 全学年・全教科が使い放題: お子さんがつまずいている単元をピンポイントで試したり、得意な教科の先取りを体験したりと、自由自在に「天神」の機能をフルで確認できます。
- PCがなくても安心の無料レンタル: ご自宅にWindowsのパソコンがなくても大丈夫。体験専用のパソコンを無料で貸し出しており、往復の送料もかかりません。
▼▼ カード登録不要!まずは資料請求・無料体験から ▼▼