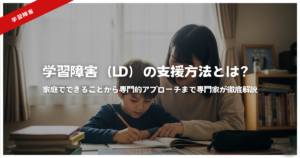学習障害(LD)の支援方法とは?家庭でできることから専門的アプローチまで専門家が徹底解説
お子さまの「がんばっているのに、なぜかできない」に寄り添うために
お子さまの学習に関して、このような悩みを抱えていませんか? もしかしたら、それは単なる「苦手」や「努力不足」ではなく、「学習障害(LD: Learning Disabilities)」の特性が関係しているのかもしれません。
学習障害とは、知的な発達に遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった特定の能力を学んだり、使ったりすることに著しい困難を示す発達障害の一つです。文部科学省の2022年の調査では、公立の小中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、学習面に著しい困難を示すとされる子どもは6.5%にのぼると報告されており、決して珍しいことではありません。
大切なのは、学習障害は本人の怠慢や努力不足が原因ではない、ということです。脳機能の何らかの偏りによって、特定のことだけが「がんばっても、できない」状態にあるのです。
この記事では、学習障害のあるお子さまを持つ保護者の皆さまが抱える不安に寄り添い、具体的な支援方法を徹底的に解説します。家庭で今日からできる工夫から、科学的根拠に基づいた学習アプローチ、そして学校や専門機関と連携する方法まで、網羅的にご紹介します。
この記事を読み終える頃には、お子さまの困難の背景を理解し、前向きな気持ちでサポートに取り組むための具体的な道筋が見えているはずです。そして、お子さま一人ひとりのペースで「できた!」を積み重ねられる学習ツールとして、私たちのデジタル教材「天神」がどのようにお役に立てるのかも、併せてご紹介します。
まずは知ることから。学習障害(LD)の3つのタイプと特性

学習障害への適切な支援は、まずその特性を正しく理解することから始まります。学習障害は、主に3つのタイプに分類されます。お子さまがどのタイプに当てはまるか、あるいは複数の特性を併せ持っているかを把握することが、効果的なサポートの第一歩です。
読字障害(ディスレクシア):文字を読むことの困難さ
ディスレクシアは、学習障害の中で最も認知されているタイプの一つです。文字や単語を正確に、かつ流暢に読むことに困難が生じます。
- 具体的な症状の例:
- 文字を一つひとつ拾って読むため、読むのに非常に時間がかかる(逐次読み)。
- 単語や文末を飛ばしたり、勝手読みをしたりする。
- 似た形の文字(例:「わ」と「ね」、「め」と「ぬ」)を混同する。
- 文章を読んでも、内容を正確に理解するのが難しい。
- 音読を極端に嫌がる。
ディスレクシアは、視力や知能の問題ではなく、文字の形と音を結びつける脳の働き(音韻処理)に偏りがあるために起こると考えられています。彼らにとって、文字はただの記号の集まりに見え、それを意味のある言葉としてスムーズに認識することが難しいのです。
書字表出障害(ディスグラフィア):文字を書くことの困難さ
ディスグラフィアは、文字を「書く」という行為に困難を伴うタイプです。頭の中ではわかっているのに、それを文字として正しくアウトプットすることができません。
- 具体的な症状の例:
- 鏡文字(左右反転した文字)を書くことが多い。
- 漢字の「へん」と「つくり」を逆にするなど、部分の配置を間違える。
- 点や線の数が違う、形が不自然な文字になる。
- マス目や罫線の中に、バランスよく文字を収めるのが苦手。
- 文章を書く際、助詞(てにをは)を抜かしたり、句読点を適切に使えなかったりする。
文字の形を記憶し、それを手の動きに変換して紙の上に再現するという、一連の運動プロセスに困難があると考えられています。また、文章を構成する力や文法を適用する力に課題がある場合もあります。
算数障害(ディスカリキュリア):計算や数的推論の困難さ
ディスカリキュリアは、数の概念の理解や計算、量の比較など、算数・数学に関連する能力に特異的な困難を示すタイプです。
- 具体的な症状の例:
- 数字を正しく読んだり書いたりできない。
- 簡単な暗算ができない、指を使わないと計算できない。
- 繰り上がり、繰り下がりの概念が理解できない。
- 図形やグラフの読み取りが苦手。
- 文章問題で、どの計算式を立てればよいかわからない。
- 時間の概念(例:時計を読む、時間の経過を把握する)が苦手。
数量を直感的に把握する力(数感覚)や、抽象的な数の概念を理解し、操作する脳の領域の働きに偏りがあると考えられています。単に計算が遅いのではなく、数の世界そのものが曖昧に見えている状態に近いのです。
特性は一人ひとり違うグラデーション
これら3つのタイプは、はっきりと分かれているわけではありません。ディスレクシアとディスグラフィアの両方の特性を持つ子もいれば、3つすべての特性を少しずつ併せ持つ子もいます。困難の程度も様々です。大切なのは、「うちの子は〇〇障害だ」と決めつけることではなく、「どのような場面で、何に困っているのか」を具体的に観察し、理解しようと努める姿勢です。
家庭でできる学習支援の基本戦略と具体的アプローチ
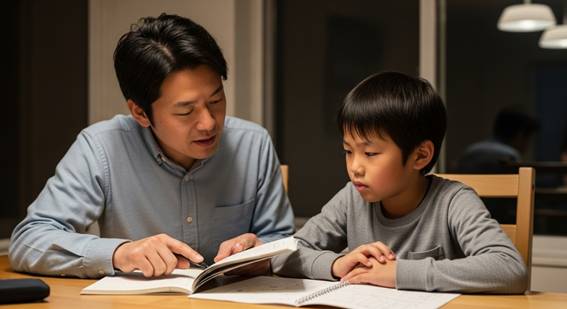
学習障害のある子どものサポートにおいて、家庭は最も重要な「安心基地」です。学校とは違い、結果や時間を気にせず、その子のペースで試行錯誤できる場所だからです。ここでは、海外の研究でも効果が示されているアプローチを交えながら、家庭で実践できる支援の基本戦略をご紹介します。
戦略1:学習環境を整える「環境調整」
子どもが学習に集中するためには、刺激が少なく、安心できる環境が不可欠です。
- 物理的な環境
- 場所: 静かで、テレビやおもちゃなど注意が逸れるものがない場所に学習スペースを設ける。
- 道具: 必要な文房具だけを机の上に置く。パーテーションなどで視界を区切るのも効果的です。
- 時間的な環境
- 時間: 毎日決まった時間に学習する習慣をつける(例:夕食後の15分間)。
- タイマーの活用: 「10分だけ頑張ろう」とタイマーをセットし、終わりが見えることで集中力を維持しやすくします。短い時間を複数回に分けるのも良い方法です。
戦略2:学習方法を工夫する「マルチモーダル・アプローチ」
学習障害の子どもは、特定の感覚(例:視覚)からの情報処理が苦手な場合があります。そこで有効なのが「マルチモーダル・アプローチ(多感覚法)」です。これは、視覚、聴覚、触覚など、複数の感覚を同時に使って学習する方法で、理解を深める効果があることが多くの研究で示されています。
- 【読みの支援】視覚と聴覚を同時に使う
- 音声教材の活用: 教科書や本の内容を音声で聞かせながら、指で文字を追わせる。目で見る情報(文字)と耳で聞く情報(音)が一致することで、文字と音の結びつきが強化されます。
- ハイライト機能: 音声が読み上げている部分の色が変わる(ハイライトされる)教材は、どこを読んでいるか視覚的にわかりやすく、ディスレクシアの子どもにとって非常に有効です。
- 【書きの支援】触覚や運動感覚を取り入れる
- なぞり書き: 大きく書いた文字の上を指でなぞる、砂や粘土で文字の形を作るなど、手触りを感じながら形を覚えます。
- ICTツールの活用: キーボード入力やタブレットの音声入力機能を使うことで、「書く」ことの物理的な困難を回避し、作文や意見表明に集中できます。
- 【計算の支援】具体物で視覚化する
- おはじきやブロック: 抽象的な数字の世界を、具体物を使って視覚的に理解させます。「3+5」であれば、3個のおはじきと5個のおはじきを実際に合わせて数える、という体験が重要です。
- 図やイラスト: 文章問題を図に描いて整理することで、問題の構造が視覚的に理解しやすくなります。
私たちのデジタル教材「天神」は、まさにこのマルチモーダル・アプローチを体現しています。
- アニメーション講義: 複雑な概念も、動きと音声でわかりやすく解説。視覚と聴覚の両方から直感的な理解を促します。
- 音声読み上げ機能(※小学生版): 問題文はもちろん、ヒントや解説まで、すべてを音声で読み上げます。さらに、読み上げている部分が自動でハイライトされるため、どこを読んでいるか一目瞭然。ディスレクシアの特性があるお子さまから「これなら一人でできる!」と絶大な支持を得ています。
- 選択式問題: 書くことが苦手なディスグラフィアのお子さまでも、クリックやタップで回答できるため、学習内容の理解に集中できます。
戦略3:成功体験を積み重ねる「スモールステップ」
学習障害の子どもにとって、何より辛いのは「できない」という失敗体験の連続です。これが自己肯定感を著しく低下させ、学習意欲そのものを奪ってしまいます。そこで不可欠なのが「スモールステップ」の原則です。
- 課題を細かく分解する
- 「漢字を10個覚える」という大きな目標ではなく、「まずこの漢字の読み方だけ覚える」「次はこの漢字の形を3回なぞってみる」というように、一つの課題を可能な限り細かく分解します。
- 「これならできる」から始める
- 学年にとらわれず、お子さまが確実に「できる」レベルまでさかのぼってスタートします。簡単な問題で「正解!」の経験を積むことが、次への意欲に繋がります。
- 強制しない
- 間違えた問題を、すぐに強制的にやり直しさせるのは逆効果です。子どもが「もう一回やってみる」と自分で思えるタイミングを待つことが大切です。
「天神」は、このスモールステップと自己肯定感を育む設計に徹底的にこだわっています。
- 超スモールステップ構成: 教科書レベルの単元をさらに細分化。一つひとつのステップが非常に小さいため、無理なく「わかった!」「できた!」を積み重ねられます。
- 自由な「戻り学習」「先取り学習」: 学年の壁がなく、小学校1年生の内容から中学校3年生の内容まで、お子さまの理解度に合わせて自由に行き来できます。苦手な単元は前の学年に戻って基礎固め、得意な教科はどんどん先へ進む、といった個別最適化が可能です。
- 強制反復なし: 間違えた後、類題に挑戦するか、解説を見るか、別の問題に進むか、すべてお子さま自身が選択できます。この「自分で選べる」という感覚が、学習への主体性を育みます。
外部の支援を上手に活用する(学校・専門機関・公的制度)

家庭でのサポートと並行して、外部の専門的な支援を活用することも非常に重要です。一人で抱え込まず、チームでお子さまを支える体制を築きましょう。
学校で受けられる「合理的配慮」
2016年に施行された「障害者差別解消法」により、学校は障害のある子どもに対して「合理的配慮」を提供することが義務付けられています。これは、学習上の困難を取り除くための、個別の調整や変更のことです。
- 合理的配慮の具体例
- テストの時間延長
- 読みやすいように拡大コピーされた、またはフォントを変更した問題用紙
- タブレットPCや音声読み上げソフトの使用許可
- 板書の撮影許可
- 口頭での試験回答
- 別室での受験
まずは学校の先生(担任、特別支援教育コーディネーターなど)に相談し、お子さまの困難を伝え、どのような配慮が可能か話し合うことが大切です。
通級指導教室(通級)の活用
通級指導教室とは、通常学級に在籍しながら、週に数時間程度、別の教室で個別の課題に応じた指導を受けられる制度です。学習障害のある子ども向けの指導では、読み書きや計算のスキルを向上させるための専門的なトレーニングが行われます。
不登校になってしまった場合の「出席扱い制度」
学習の困難から学校へ行く意欲を失い、不登校になってしまうケースも少なくありません。その場合でも、自宅での学習が一定の要件を満たせば、学校の出席として認められる「出席扱い制度」があります。
- 要件のポイント
- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること。
- ICT等を活用した学習活動であること。
- 学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。
- 校長が対面指導や学習状況の評価が適切に行えると判断すること。
この制度を利用する際、「日々の学習記録を客観的な形で学校に報告すること」が非常に重要になります。
「天神」には、いつ、どの単元を、どれくらいの時間学習したかを記録し、「学習報告書」としてワンタッチでPDF出力できる機能があります。これを学校に提出することで、日々の学習状況をスムーズに報告でき、出席扱い制度の活用を力強くサポートします。不登校で悩むご家庭にとって、大きな安心材料となっています。
専門機関への相談
家庭や学校だけで解決が難しい場合は、専門機関に相談することも検討しましょう。
- 医療機関: 児童精神科や小児神経科などで、学習障害の診断を受けることができます。
- 教育支援センター(適応指導教室): 各市町村が設置する、不登校児童生徒への支援を行う機関です。
- 発達障害者支援センター: 発達障害に関する相談に応じ、様々な情報提供や助言を行っています。
- 放課後等デイサービス: 障害のある子どもを対象に、放課後や長期休暇中に生活能力向上のための訓練などを提供する福祉サービスです。
「天神」は、教材を売って終わりではありません。ご契約前からご契約後まで、専門スタッフによる無料のサポート体制を整えています。スタッフの中には児童発達支援士や発達障害支援アドバイザーの有資格者も在籍。教材の使い方だけでなく、お子さまの学習の進め方や日々の悩みについて、いつでも無料でご相談いただけます。自動音声なしで直接担当者につながる安心感も、サポート満足度98.5%(※2020年アンケート)という高い評価に繋がっています。
学習障害の子どもを支える上での大切な心構え
具体的な支援方法と並行して、保護者の心構えも非常に重要です。お子さまが安心して学びに向かうための土台となる、3つの大切なポイントをお伝えします。
「できないこと」ではなく「できること」に目を向ける
学習障害の特性があると、どうしても「できないこと」ばかりが目についてしまいます。しかし、できないことを叱ったり、無理にやらせたりしても、状況は好転しません。むしろ、お子さまが本来持っている素晴らしい才能や「できること」を見つけ、それを存分に褒めてあげてください。
など学習面以外の長所を認めることで、子どもの自己肯定感が育まれます。その自信が、苦手なことに挑戦するエネルギーになるのです。
結果ではなくプロセスを褒める
「100点を取ったから偉い」のではなく、「10分間、集中して机に向かえたことが素晴らしい」というように、結果ではなく、そこに至るまでの努力や姿勢(プロセス)を具体的に褒めましょう。
学習障害の子どもは、人一倍の努力をしても、結果に結びつかないことが多々あります。その見えない頑張りを認めてもらえることが、何よりの救いになります。
他の子と比べない
他の子と比べることは、保護者にとっても子どもにとっても、百害あって一利なしです。比べるべきは、他の誰でもなく「昨日のお子さま」です。
お子さま自身の成長に目を向け、その小さな一歩を一緒に喜ぶことが、前進するための何よりの原動力となります。
「天神」は、こうしたご家庭の教育方針を最大限に尊重し、サポートするために作られています。
- 個別の進捗管理: 兄弟姉妹で利用する場合も、成績や学習の進捗は完全に個別に記録・管理されます。それぞれのペースで、誰かと比べられることなく学習を進められます。
- 兄弟姉妹は無料: 1人分の料金で、何人でも兄弟姉妹が無料で利用できます。これにより、すべてのお子さまに質の高い学習機会を提供しながら、家計の教育コストを抑えることができます。
- 買い切り型: サブスクリプション型ではないため、一度購入すれば月々の支払いを気にすることなく、お子さまのペースでじっくりと、そして長くご活用いただけます。
お子さまの「学びたい」気持ちを諦めないために
学習障害の支援は、まさに十人十色です。この記事でご紹介したように、その子の特性を深く理解し、「環境調整」「マルチモーダル・アプローチ」「スモールステップ」といった戦略を組み合わせながら、最適な方法を粘り強く探していく必要があります。
そして何より大切なのは、お子さまの自己肯定感を守り、育むことです。「自分はダメな人間じゃないんだ」「やればできるんだ」という感覚が、困難を乗り越えるための最も強い力となります。
しかし、これらの理想的な支援を、保護者の方だけで、日々の忙しさの中で実践し続けるのは、決して簡単なことではありません。
- 「音声で読み上げてくれる教材なんて、どこにあるの?」
- 「うちの子に合うレベルまで細かく分解された問題集が見つからない…」
- 「不登校の出席扱いのために、毎日学習記録をつけるのは大変…」
こうした悩みを一挙に解決し、ご家庭での理想的な学習環境づくりを力強くサポートするのが、私たちが開発したデジタル学習教材「天神」です。
- 障害児教育の専門家も推薦する、発達の凹凸に配慮した設計
- 視覚と聴覚で理解を助けるアニメーション講義と音声読み上げ+自動ハイライト(※小学生版)
- 学年に関係なく「戻り学習」「先取り学習」が自由自在
- 「できた!」を積み重ねる超スモールステップと、やる気を削がない強制反復なしの仕組み
- 不登校の出席扱いにも対応できる学習報告書の簡単出力機能
- 専門スタッフによる無料相談で、導入後も安心
もし、この記事を読んで「うちの子にも、天神が合うかもしれない」と少しでも感じていただけたなら、ぜひ一度、無料体験をお試しください。
無料体験では、全学年・全教科のすべての機能をじっくりとお試しいただけます。パソコンがないご家庭には、体験用のパソコンを往復送料無料で無料レンタル。クレジットカードの登録も不要です。体験後に「うちには合わない」と感じた場合は、アンケートで「購入予定なし」と回答いただければ、しつこい営業のお電話をすることも一切ありません。
お子さまの未来の可能性を広げるための第一歩を、まずはリスクなく踏み出してみませんか? お子さまが「学ぶって楽しいかも!」と感じる瞬間を、ぜひ「天神」で体験してみてください。
▼▼今すぐ「天神」の無料体験を申し込む▼▼