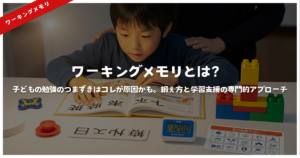ワーキングメモリとは?子どもの勉強のつまずきはコレが原因かも。鍛え方と学習支援の専門的アプローチ
もし、あなたのお子様にこのような様子が見られるなら、その背景には「ワーキングメモリ」の働きが関係しているかもしれません。
この記事では、近年、教育や発達支援の現場で注目されている「ワーキングメモリ」について、その基本から、子どもの学習に与える影響、そして家庭でできる効果的な鍛え方や学習支援の方法まで、専門的な知見を交えながら分かりやすく解説します。
お子様の「なぜ?」を理解し、明日からの関わり方を変えるヒントがここにあります。ぜひ最後までお読みいただき、お子様の可能性を最大限に引き出す一歩を踏み出してください。
ワーキングメモリとは?「脳のメモ帳」の働きを分かりやすく解説

ワーキングメモリ(Working Memory)とは、一言でいえば「情報を一時的に記憶し、同時に処理するための脳の機能」です。よく「脳のメモ帳」や「頭の中の作業台」に例えられます。
短期記憶が単に情報を短時間だけ覚えておく「保管庫」だとすれば、ワーキングメモリは、その保管庫から情報を取り出し、計算したり、並べ替えたり、他の情報と結びつけたりする「作業スペース」の役割を担っています。
例えば、以下のような日常の場面でワーキングメモリは活発に働いています。
- 会話: 相手の話を聞き(情報を保持)、その内容を理解し(情報を処理)、自分の意見を組み立てて話す。
- 計算: 「13 × 4」という計算で、まず「3×4=12」を計算して「2」を書き、「1」を繰り上がりとして覚えておき(保持)、次に「1×4」の計算結果と先ほどの「1」を足す(処理)。
- 料理: レシピを読み(保持)、次にやるべき工程を考えながら(処理)、今やっている作業を進める。
このように、私たちは意識することなく、常にワーキングメモリを使って生活や学習を行っているのです。
世界的に有名な「ワーキングメモリモデル」
このワーキングメモリの概念を理論的に体系化したのが、イギリスの心理学者アラン・バッデリー(Alan Baddeley)氏とグレアム・ヒッチ(Graham Hitch)氏です。彼らが1974年に提唱したモデルは、現在もワーキングメモリを理解する上での基礎となっています。
彼らのモデルでは、ワーキングメモリは単一の機能ではなく、複数の要素からなるシステムだと考えられています。
- 中央実行系 (Central Executive): 全体の司令塔。どの情報に注意を向け、どのように処理するかをコントロールします。
- 音韻ループ (Phonological Loop): 耳から入った言葉や、頭の中で繰り返す言葉などの「音」の情報を一時的に保持します。電話番号の復唱などが典型例です。
- 視空間スケッチパッド (Visuospatial Sketchpad): 目から入った映像や、物の位置関係などの「見た目」の情報を一時的に保持します。頭の中で地図を描くときなどに使われます。
これらの部品が連携することで、私たちは複雑な課題をこなすことができるのです。

もしかして?ワーキングメモリが弱い子どもの7つの特徴【チェックリスト】
ワーキングメモリの働きが弱いと、日常生活や学習において様々な困難が生じやすくなります。もしお子様に当てはまるものが多い場合、ワーキングメモリの働きをサポートする工夫が必要かもしれません。
□ 1. 指示を聞き漏らす、複数の指示を覚えられない
「おもちゃを片付けて、手を洗って、それからリビングに来てね」といった2つ以上の指示を出すと、最初の一つしかできなかったり、途中で何をするか忘れてしまったりする。
□ 2. 忘れもの・失くしものが多い
持ち物の管理が苦手で、学校に持っていくべきものや、宿題を頻繁に忘れる。学校から持ち帰るべきものを置いてきてしまうことも多い。
□ 3. 会話が噛み合わないことがある
相手の話を最後まで聞かずに話し始めたり、話の途中で話題が飛んでしまったりする。話の要点を掴むのが苦手なため、質問に的確に答えられないこともある。
□ 4. 勉強でケアレスミスが多い
計算の途中で繰り上がりを忘れる、文章問題で条件を読み飛ばす、漢字を写し間違えるなど、注意深く行えばできるはずの間違いを繰り返す。
□ 5. 文章を読むのが苦手・遅い
文章を読んでいる最中に、前の文の内容を忘れてしまうため、何度も読み返す必要がある。そのため、読解に時間がかかったり、内容を正確に理解するのが難しかったりする。
□ 6. 板書を写すのが極端に遅い
黒板の文字を見て(保持)、ノートに書き写す(処理)という作業の切り替えがスムーズにできない。どこまで写したか分からなくなったり、文字を覚えている時間が短かったりするため、非常に時間がかかる。
□ 7. 物事の段取りを立てるのが苦手
宿題をどの順番でやるか、遊びの準備をどう進めるかなど、見通しを立てて行動するのが苦手。行き当たりばったりで行動し、途中で混乱してしまうことがある。
これらの特徴は、単なる「不注意」や「やる気の問題」ではなく、ワーキングメモリという脳機能の特性に起因している可能性があります。叱るのではなく、その特性を理解し、適切なサポートをしてあげることが何よりも重要です。
ワーキングメモリと学習の深い関係|算数・国語が苦手なのはなぜ?
ワーキングメモリの容量や効率は、学力、特に「読む力」と「計算力」に強く関連することが多くの研究で示されています。ワーキングメモリが弱いと、なぜ学習でつまずきやすくなるのでしょうか。教科ごとに具体的に見ていきましょう。
算数・数学:「計算」と「文章問題」で負荷がかかる
算数や数学は、ワーキングメモリを特に多く使う教科です。
- 筆算・暗算: 繰り上がりや繰り下がりを一時的に覚えておきながら、次の計算を進める必要があります。ワーキングメモリの容量が小さいと、この「覚えておく」という部分でつまずき、計算ミスが頻発します。
- 文章問題: 問題文を読み、書かれている数字や条件を記憶し(保持)、どの計算式を立てるべきかを考え(処理)、実際に計算するという複数のステップが必要です。一つ一つのステップでワーキングメモリに大きな負荷がかかるため、途中で何をすべきか分からなくなってしまいます。
国語:「読解」と「作文」で情報処理が追いつかない
国語もまた、ワーキングメモリが重要な役割を果たします。
- 長文読解: 文と文の関係性や登場人物の言動などを記憶しながら読み進めないと、全体のストーリーや筆者の主張を理解できません。ワーキングメモリが弱いと、読んでいるそばから内容を忘れてしまい、「結局何が言いたいの?」という状態に陥りがちです。
- 作文・記述問題: 「何を書くか」というテーマ(保持)と、「どういう言葉で、どの順番で書くか」という構成(処理)を同時に考えなければなりません。頭の中が整理できず、文章が支離滅裂になったり、短い文しか書けなかったりします。
英語:単語・文法の暗記と運用が難しい
英語学習では、新しい単語や文法ルールを覚え、それを実際に使いこなす必要があります。
- リスニング: 聞こえてくる英文を一時的に記憶し、意味を理解する作業は、まさに音韻ループの働きそのものです。
- 長文読解・英作文: 国語と同様に、文の構造を理解したり、文章を組み立てたりする際にワーキングメモリを駆使します。
このように、ほとんどの学習活動はワーキングメモリを土台としています。そのため、ワーキングメモリへの支援は、学力全体の底上げに繋がる可能性があるのです。
発達障害(ADHD・LD)とワーキングメモリの関係性
ワーキングメモリの弱さは、発達障害、特にADHD(注意欠如・多動症)やLD(学習障害)のある子どもたちに多く見られる特性の一つです。
- ADHD: ADHDの中心的な困難である「不注意」は、ワーキングメモリの司令塔である「中央実行系」の機能不全と深く関連していると考えられています。注意を維持したり、行動をコントロールしたりすることが難しいため、情報の保持や処理がうまくいかないのです。
- LD:
- 読字障害(ディスレクシア): 文字と音を結びつける「音韻処理」の困難が背景にあることが多く、これはワーキングメモリの「音韻ループ」の働きと関連しています。
- 算数障害(ディスカリキュリア): 数字の概念の理解や、計算手順の記憶が困難なケースが多く、ワーキングメモリ全般の弱さが影響していると考えられています。
もちろん、ワーキングメモリが弱いからといって必ずしも発達障害があるわけではありません。しかし、もし発達障害の診断を受けている、あるいはその傾向があるお子様の場合、ワーキングメモリへの配慮は学習支援の重要な鍵となります。
家庭でできる!子どものワーキングメモリを鍛える・サポートする9つの方法

ワーキングメモリは、脳の機能であると同時に、トレーニングによってその効率を高めたり、工夫によって負荷を軽減したりすることが可能です。ここでは、日常生活の中で気軽に取り組める方法と、学習を直接サポートする方法をご紹介します。
日常生活で楽しくトレーニング
- おつかい・お手伝いを頼む: 「牛乳と、卵と、パンを買ってきて」のように、覚えるものを少しずつ増やしていく。メモを持たずに挑戦することで、記憶力と実行力を鍛えます。
- しりとり・連想ゲーム: 「りんご→ゴリラ→ラッパ」のように、前の言葉を覚えて次の言葉を考えるしりとりは、音韻ループの良いトレーニングになります。
- カードゲーム・ボードゲーム: 神経衰弱は場所を記憶する「視空間スケッチパッド」を、戦略的なゲームは先の展開を予測する「中央実行系」を鍛えます。
- 料理の手伝い: 「次に何を入れるんだっけ?」と手順を確認させたり、材料を計量させたりする作業は、ワーキングメモリをフル活用します。
- 本の読み聞かせと質問: 読み聞かせの後に、「主人公は誰と会ったっけ?」など簡単な質問をすることで、物語の内容を記憶し、引き出す練習になります。
学習の負荷を減らすサポート
- 指示は「短く」「一つずつ」: 一度に多くのことを伝えず、「まず、教科書の5ページを開いて」のように、具体的かつ単一の指示を心がけます。
- 視覚的なツールを活用する: やるべきことを付箋に書いて貼る「To-Doリスト」や、時間の流れが目に見える「タイマー」は、ワーキングメモリの外部メモリとして非常に有効です。
- 手順を細かく分解する(スモールステップ): 算数の文章問題なら、「①問題文を声に出して読む」「②分かっていることに線を引く」「③聞かれていることに波線を引く」のように、一つの大きな課題を小さなステップに分解してあげます。
- 声に出して学習する: 教科書を音読したり、計算の過程を口に出したりすることで、聴覚情報(音韻ループ)も活用でき、記憶に残りやすくなります。
これらの方法は有効ですが、保護者の方が常に隣について教えるのは現実的に難しい場面も多いでしょう。また、トレーニングが「やらされ感」に繋がると、子どもの意欲を削いでしまう可能性もあります。
そこで、テクノロジーを活用した学習支援が、新たな選択肢として注目されています。
ワーキングメモリが弱い子の学習にこそ「天神」が最適な理由
家庭でのサポートには限界がある。塾のペースにはついていけない。でも、子どもの学びは止めさせたくない――。そんな保護者様の悩みに応えるために開発されたのが、デジタル学習教材「天神」です。
「天神」は、ワーキングメモリへの負荷を極限まで減らし、子どもが「自分にもできた!」という成功体験を積み重ねられるように、発達障害教育の専門家の知見も取り入れて設計されています。
なぜ「天神」がワーキングメモリに課題を抱えるお子様に最適なのか、その理由を5つのポイントでご紹介します。
1. 「音声読み上げ+自動ハイライト」で“読む”負担を激減
ワーキングメモリが弱い子にとって、文章を読むこと自体が大きなエネルギーを消費します。「天神」の小学生版には、問題文や選択肢、解説まで、すべてのテキストを滑らかな音声で読み上げる機能が搭載されています。
読み上げている箇所が自動でハイライト(色付け)されるため、子どもは「目」と「耳」の両方からスムーズに情報をインプットできます。これにより、「文字を読む」という作業負荷から解放され、問題の内容を理解することに集中できるのです。これは、視覚情報と聴覚情報を統合して処理するワーキングメモリの働きを、システムが強力にサポートしている状態と言えます。
2. 「超スモールステップ」で、一度に処理する情報量を最小化
一度に多くの情報を処理するのが苦手な子のために、「天神」は学習内容を非常に細かいステップ(超スモールステップ)に分解しています。
- ① アニメーション講義で直感的に理解
- ② ポイント解説で要点を確認
- ③ 1問1答形式で問題演習
このように、学習の流れが細分化されているため、ワーキングメモリへの負荷が少なく、一つひとつ着実にクリアしていくことができます。「分かった!」「できた!」という小さな成功体験が、子どもの自己肯定感を育み、学習意欲を引き出します。
3. 「強制反復なし」で、子どものペースとやる気を尊重
多くのデジタル教材では、間違えた問題を「できるまで」強制的に繰り返させることがあります。しかし、ワーキングメモリが原因でミスをする子にとって、これは「また失敗した」というネガティブな体験の繰り返しになりかねません。
「天神」は、間違えた後にやり直すかどうかを子ども自身が選べます。すぐに類題に挑戦してもいいし、もう一度解説に戻ってもいい。この「自己決定権」が、学習への主体性を育て、失敗を恐れずに挑戦する気持ちを支えます。
4. 学年の壁がない「戻り学習」で、根本的なつまずきを解消
算数のつまずきの原因が、実は2学年前に習った単元にあった、というケースは少なくありません。「天神」は全学年・全範囲の学習が自由に行えるため、お子様の本当のつまずきの原因までさかのぼって、基礎から学び直すことができます。ワーキングメモリの弱さを補うためには、土台となる基礎知識を盤石にすることが不可欠です。
5. 専門スタッフによる「無料サポート」で、保護者の不安も解消
「天神」は教材を売って終わりではありません。児童発達支援士などの有資格者が在籍する専門スタッフが、契約前も契約後も、電話やLINEで無料で学習相談に応じています。
「うちの子に合った進め方は?」「この機能はどう使えば効果的?」といった疑問に、すぐに担当者が直接対応。保護者の方が一人で悩みを抱え込む必要はありません。
ワーキングメモリへの配慮は、特別なことではありません。すべての子どもが「自分に合った方法」で学べる環境を整えることです。「天神」は、そのための強力なツールとなります。
まずは無料体験から|お子様に合うかどうかをじっくりご判断ください
「うちの子にデジタル教材は合うだろうか…」
「パソコンの操作が苦手だけど大丈夫?」
そんな不安をお持ちの方のために、「天神」では充実した無料体験をご用意しています。
- PC無料貸出: ご自宅にWindowsパソコンがない場合でも、体験専用PCを無料でお貸し出しします(往復送料も不要)。
- 全機能・全教科を体験可能: 小学生・中学生版の全学年・全教科のすべての機能を、期間中じっくりお試しいただけます。お子様がどの単元でつまずいているのか、どの機能に興味を示すのかを、ご家庭でしっかり確認できます。
- しつこい営業は一切なし: 体験後のアンケートで「購入予定なし」とご回答いただいた方には、原則としてご連絡いたしません。安心してお試しください。
ワーキングメモリの課題に対しては、早期の適切なサポートがお子様の将来の可能性を大きく広げます。「天神」が、その一助となれるかもしれません。
▼まずは資料請求で詳しい情報をご確認ください▼